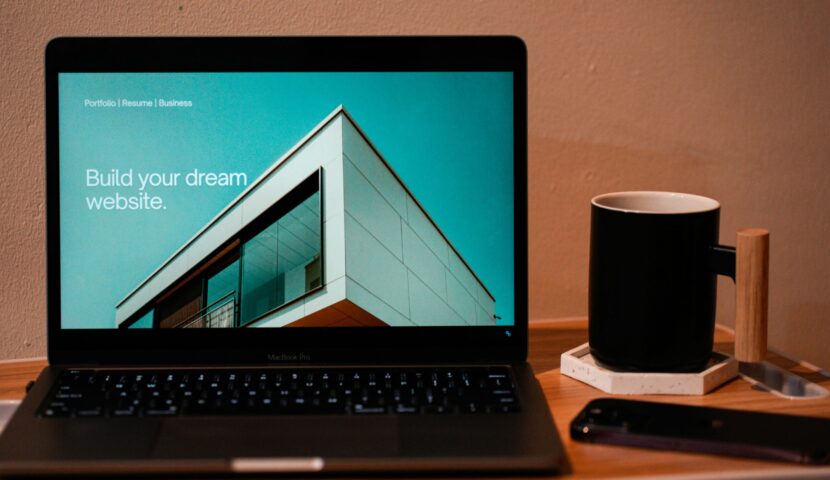「ランディングページを作りたいけれど、制作費はいくらが妥当なんだろう?」
そんな疑問を抱いて検索したあなたは、すでに一歩先に進んでいます。
実際、ランディングページ(以下、LP)の制作費用は数万円から百万円を超えるものまで幅が広く、「なぜそんなに差があるのか」「何を基準に選べばいいのか」が分かりにくいのが現実です。特に初めて依頼する方にとっては、相場の感覚がつかめないまま見積もりを受け取り、金額だけで判断して後悔してしまうケースも少なくありません。
本記事では、LP制作の相場の全体像と費用を左右する要素を分かりやすく解説しながら、価格帯別の特徴や発注時の注意点、費用対効果を最大化するコツを詳しく紹介します。また、中小企業や個人事業主の方に向けて、信頼できる制作会社を見極める方法や、費用を抑えながら質を保つ発注のコツも丁寧に解説します。
さらに、複数社比較を前提にした発注支援を行う「あいみつ相談室」の活用方法も紹介し、LP制作を検討している方が安心して最適な選択をできるようサポートします。
この記事を読めば、
- LP制作の費用が高い・安い理由が理解できる
- 自社の目的に合った発注先を選べる
- 相場を知った上で、無駄のない予算設計ができる
という状態に到達できるはずです。
それでは、具体的に「LP制作の相場とは何か」から見ていきましょう。
LP制作の相場が“幅広い”理由
費用のブレを生む要因を解きほぐす
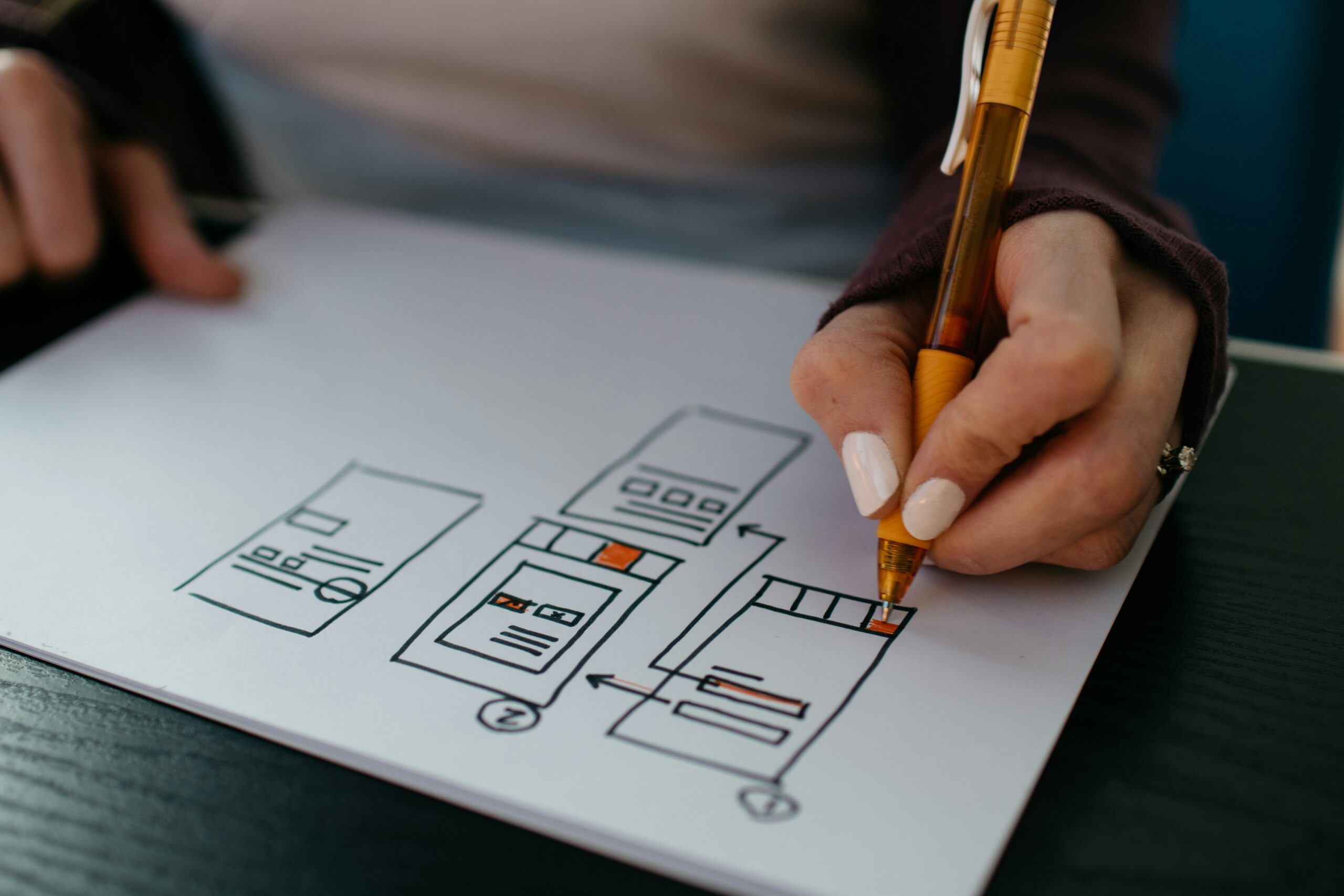
ランディングページ(LP)の制作費は、安ければ10万円前後、高ければ100万円を超えることもあります。この価格差は単に「業者によって違う」という話ではなく、制作の目的・構成・体制・発注内容など、複数の要因が絡み合って生まれるものです。ここでは、その主な要因を一つずつ分解して見ていきましょう。
LP制作コストを決める主要要素(企画/設計/素材/機能/改善など)
LP制作の費用を左右する最大の要素は、「どこまでを依頼範囲に含めるか」です。単にデザインやコーディングだけを行うのか、それとも戦略設計や構成案作成、コピーライティング、公開後の改善まで含めるのかで費用は大きく変わります。
たとえば、広告の成果を最大化するLPを作る場合、ユーザー心理の分析や訴求設計などの上流工程が欠かせません。これらを専門のマーケターやディレクターが担当する場合、その分の人件費が上乗せされます。さらに、動画やアニメーションを用いた表現、問い合わせフォームやCRM連携などの機能面も、コスト増につながる要素です。
一方で、テンプレートを使ってシンプルなデザインを作る場合は、設計やライティングの工数を減らせるため、費用を抑えやすくなります。どの工程をどこまで求めるかが、価格の分かれ道と言えるでしょう。
発注先タイプ別コスト構造(フリーランス/中小/大手/広告代理店)
同じ内容を依頼しても、発注先によって見積もりが異なるのは当然のことです。フリーランスの場合、少人数で運営しているため人件費が低く、比較的安価で引き受けてくれる傾向があります。ただし、担当者が一人のため、対応範囲や納期には限界があることも考慮しなければなりません。
中小制作会社は、デザインやコーディングに加えて、マーケティング視点を持ったディレクションを行うケースが多く、30万〜60万円程度が中心価格帯です。費用とクオリティのバランスを重視するなら、この層がもっとも選ばれやすいでしょう。
一方、大手制作会社や広告代理店になると、専門チーム体制で分析・設計・改善運用までを一気通貫で行うため、100万円を超える案件も珍しくありません。ブランド戦略や広告運用との連動まで任せたい企業に適していますが、単発のキャンペーンLPなどにはオーバースペックになる場合もあります。
仕様・機能・素材準備の有無で変わる価格差
LP制作における“仕様”は、費用を最も明確に左右する要素の一つです。たとえば、画像やテキスト素材を依頼者が用意できるかどうかで見積もりが変わります。写真撮影・動画制作・イラスト制作を含める場合は、10万円単位で上乗せされることも珍しくありません。
また、ユーザー体験を高めるためのアニメーションやスクロール演出、パララックス効果、フォームの自動入力機能なども費用を押し上げるポイントです。とくに近年ではスマートフォン最適化(レスポンシブ対応)や、Googleタグ・広告連携などの実装が必須になっているため、コーディングの精度が求められます。
逆に、これらの機能を省き、既存テンプレートをベースにしたシンプルな構成であれば、デザインと実装を含めても10〜20万円台で収まるケースもあります。つまり、LP制作の“相場”は固定されたものではなく、目的と求める成果によって柔軟に変動するものだと言えるでしょう。
このように、LP制作の価格を決めるのは「誰に」「どの範囲まで」「どんな目的で」依頼するかという3つの軸です。費用の高低だけに注目するのではなく、目的に対して適正なコストかどうかを判断する視点を持つことが、後悔しない発注の第一歩になります。
実例で見る“相場レンジ別”の内容と特徴

LP制作の費用は幅が広いため、「自社にとってどの価格帯が適正なのか」が分かりづらいと感じる人も多いでしょう。ここでは、一般的な価格帯ごとに「どんな内容が含まれるのか」「どんな企業や目的に向いているのか」を分かりやすく整理します。数字の大小だけで判断するのではなく、費用の中身を理解することが重要です。
~10万円:テンプレート活用・最低限仕様
10万円以下で依頼できるLPは、主にテンプレートを活用した簡易制作が中心です。既存デザインをベースに画像とテキストを差し替えるだけのケースが多く、制作スピードが早いのが特徴です。
ただし、戦略設計や構成案の提案、コピーライティングなどの“成果を左右する要素”は含まれないことがほとんどです。そのため、「とりあえず形にしたい」「短期間でキャンペーンを実施したい」といった場合には適していますが、本格的にコンバージョンを狙うLPには不向きです。
また、修正対応や公開後のフォローが限定的なことが多いため、後から改修する場合は追加費用が発生しやすい点にも注意が必要です。
10~30万円:デザイン重視だが上流工程は限定的
この価格帯は、中小規模の制作会社や経験豊富なフリーランスが多く対応しており、ある程度のオリジナルデザインが可能です。構成案の提案や軽微なライティングサポートを含む場合もあります。
一方で、マーケティング設計や競合分析といった上流工程は含まれないことが一般的です。つまり「見た目の良いLPは作れるが、成果を最大化するための戦略までは踏み込めない」レンジです。
デザインにこだわりたいが、予算を大きくかけられない中小企業や個人事業主に適しており、広告テストやMVP的なプロジェクトに向いています。
30~60万円:企画~実装までワンストップで任せる中核レンジ
LP制作の“相場の中心”となるのがこの価格帯です。企画・構成・コピーライティング・デザイン・コーディングまで一貫して対応できる制作会社が多く、全体のクオリティバランスが取れています。
特に30万円後半〜50万円前後のプランでは、ヒアリングをもとにした訴求軸設計や、ABテストを見据えた構成提案を含むこともあります。社内にマーケティング担当がいない企業でも、プロの視点からLPの目的設計を行ってもらえるため、初めて外注する場合にもおすすめです。
また、公開後の簡易修正や効果測定のサポートがセットになっているケースもあり、費用対効果を重視する企業には最も現実的なレンジといえるでしょう。
60万円以上:マーケティング支援・改善運用込みの高付加価値プラン
60万円を超えるLP制作は、単なるデザインや構築ではなく、戦略立案や運用改善までを含めた包括的なプロジェクトになります。リサーチ・ペルソナ設計・競合分析・コピー開発などを踏まえ、広告運用やSEOと連携させた「売るための設計」が組み込まれるのが特徴です。
この価格帯では、データ分析やCVR改善を継続的に行う運用支援をセットにするケースも多く、成果にコミットする姿勢が求められます。特に、広告予算を月数十万円以上かける企業や、事業成長を目的としたLP制作には最適です。
ただし、高額だからといって必ず成果が出るわけではありません。契約前に「どの工程が含まれているか」「どこまでサポートしてもらえるか」を明確にしておくことが重要です。
業界別・用途別の価格傾向(B2B、士業、美容、キャンペーンLP等)
LP制作の相場は、業界や目的によっても変わります。たとえば、B2Bや士業向けLPは、専門知識が必要なためコピーライティングや構成に時間を要し、単価が高くなりやすい傾向があります。
一方で、美容・食品・ファッションなどのB2C業界では、ビジュアル重視のデザイン性が求められることが多く、撮影費や画像制作費が加わるケースがあります。また、短期キャンペーン用のLPは、スピード重視のため簡易構成で費用を抑えやすい反面、継続的な改善や運用は別契約になることが多いです。
このように、同じ「LP制作」といっても、業界や目的が違えば適正価格は異なります。自社のビジネス目的とターゲットに合った費用感を知ることが、正しい相場理解につながるのです。
LP制作の費用を比較するときは、「どのレンジにどんな価値が含まれているか」を見極めることが大切です。安さだけで判断せず、目的・サポート範囲・実績などのバランスを総合的に見て選ぶことが、成果につながるLP制作の第一歩になります。
見積もりでよく見る内訳項目と“隠れコスト”の見抜き方
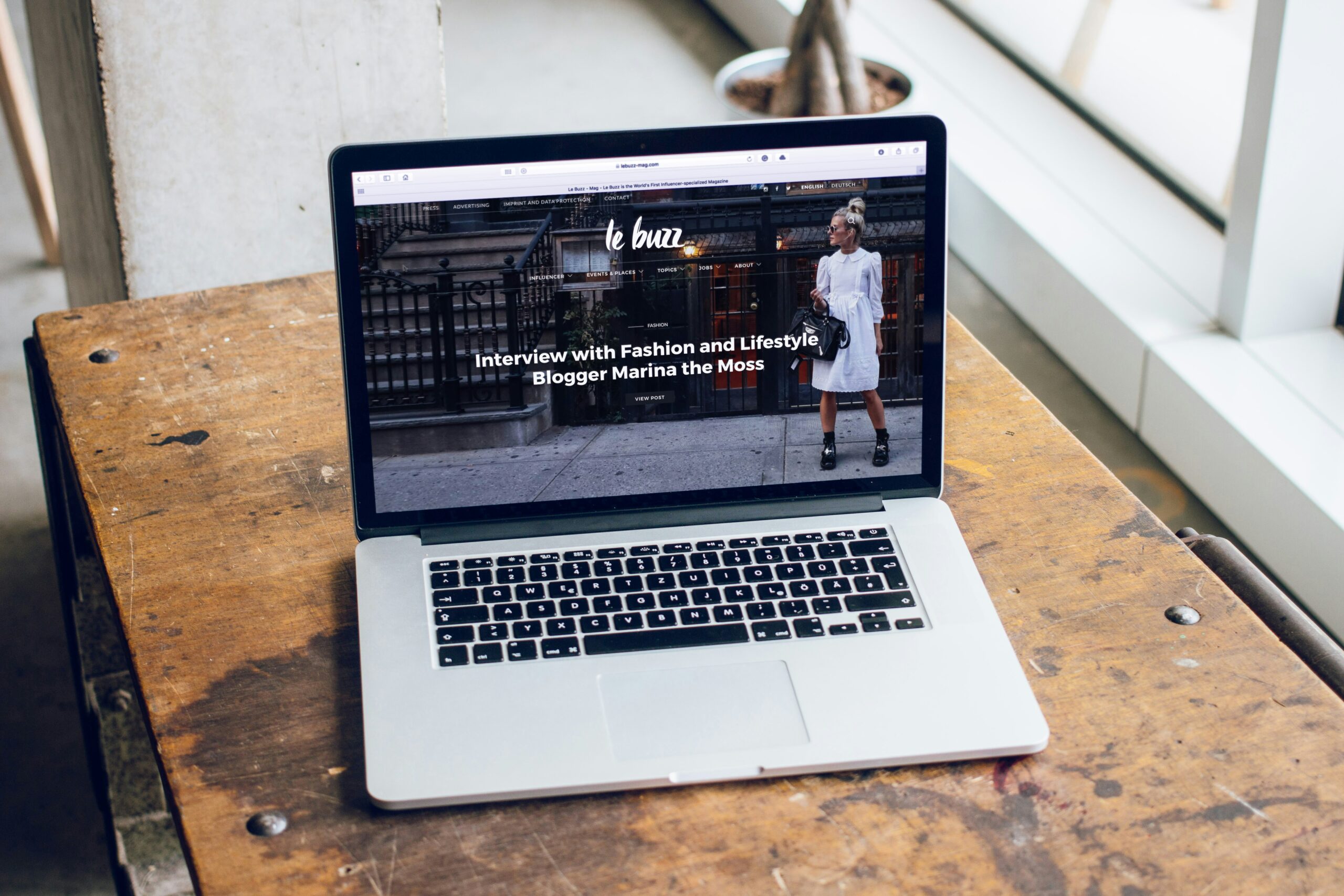
LP制作の費用を理解するうえで欠かせないのが、見積書に記載された「内訳項目」を正しく読み取ることです。
一見シンプルに見えても、どの工程が含まれているのか、どこまでサポートしてもらえるのかを把握していなければ、後から思わぬ追加費用が発生することもあります。ここでは、代表的な項目の意味や、注意すべき“隠れコスト”について詳しく解説します。
見積もり内訳の標準要素(戦略設計・構成案・コピー・デザイン・実装・テスト・公開)
LP制作の見積書には、主に次のような項目が含まれます。
- 戦略・構成設計費
- コピーライティング・原稿作成費
- デザイン制作費
- コーディング・システム実装費
- テスト・ブラウザ確認・公開作業費
- 修正対応費
- 保守・運用費(オプション)
まず「戦略・構成設計費」は、LPの目的設定やコンバージョン導線を設計する工程です。ここを軽視すると、見た目は整っても成果の出ないLPになりかねません。
次に「コピーライティング・原稿作成費」は、訴求力を生み出す要となる部分。プロのライターが手掛ける場合は、5万円前後から10万円以上になることもあります。
「デザイン制作費」は、ブランドトーンに合わせたビジュアル設計やUI調整などを含みます。オリジナルデザインであれば15〜30万円ほどが目安です。
「コーディング・システム実装費」は、HTML・CSS・JavaScriptでの構築やフォーム設置、レスポンシブ対応などを指し、10〜20万円程度が一般的です。
最後に「テスト・公開作業」では、ブラウザ検証やサーバー設定、SSL設定などの技術的工程が行われます。これを省くと、公開後に表示崩れやフォーム不具合が起きるリスクがあります。
見積書では、これらが明確に分かれて記載されているかが重要です。
一式表記になっている場合、どの範囲が含まれているかを必ず確認しましょう。
契約形態・支払条件・保証制度を確認すべきチェックポイント
意外と見落とされやすいのが、契約形態や支払条件、修正・保証に関する取り決めです。制作会社によっては、契約時に全額前払いを求めるところもあれば、着手金と納品後の分割払いに対応しているところもあります。
また、「修正対応回数」が明記されているかどうかも確認すべきポイントです。修正回数が制限されている場合、追加対応のたびに費用が発生することがあります。特にライティングやデザイン修正は見積もり外になりやすく、想定外の出費につながる要因です。
保証制度についても事前に確認しましょう。公開後の不具合にどこまで対応してもらえるか、期間や範囲を契約書で明示しておくと安心です。
支払いや契約条件は金額以上にトラブルになりやすい部分です。「安い見積もりだと思ったら、契約条件で縛られていた」という事態を避けるためにも、細部の確認を怠らないようにしましょう。
異常に安すぎる・高すぎる見積もりのリスクと見分け方
見積もりを複数社から取ると、驚くほど価格差が出ることがあります。たとえば、同じ仕様なのに10万円台の提案と60万円の提案が届くことも珍しくありません。
そのようなときは、「なぜ安いのか」「なぜ高いのか」の理由を冷静に見極めることが大切です。
あまりに安い見積もりは、以下のようなリスクを含むことがあります。
- テンプレート流用によるクオリティ低下
- デザインやコピーの修正対応が別料金
- 納期を優先し品質が犠牲になる
- 公開後のサポートなし
逆に、極端に高い見積もりの場合は「広告運用・コンサル・改善分析」などの付加価値が含まれているケースもありますが、内容が不明瞭なまま高額になっている場合もあるため、必ず内訳を明確にしてもらいましょう。
見積もり金額を判断するときは、“目的に対して妥当かどうか”を基準にするのがポイントです。金額の大小よりも、その中に含まれる工程と成果への影響を照らし合わせて評価することで、納得感のある選択ができます。
納期・スケジュールの目安と遅延リスク
費用だけでなく、納期スケジュールも見積もり時の重要な要素です。一般的に、LP制作の期間は2〜6週間が目安とされていますが、要件や修正回数によって前後します。
テンプレートベースの簡易LPであれば最短1〜2週間、本格的な戦略設計を伴うLPでは1〜2カ月かかることもあります。
特に、ライティングや撮影、フォーム連携など外部作業が発生する場合は、スケジュールに余裕を持つことが大切です。
また、依頼側の確認・フィードバックの遅れが納期延長につながることも多いため、制作会社とのコミュニケーションフローを明確にしておきましょう。
「いつ何を決めるのか」「どの段階で修正できるのか」を事前に共有しておくことで、トラブルを防ぎ、予定どおりにLPを公開できます。
LP制作の見積もりを正しく理解することは、無駄なコストを削減する最初のステップです。
数字だけでなく、内容・条件・サポート体制を比較しながら、「何にお金を払うのか」を把握することで、初めて本当の意味で“相場を理解する”ことができるのです
LPは“投資”として捉えるべき理由とROIの見方

多くの企業がランディングページ制作を「費用」として捉えがちですが、実際には“投資”として考えることが成果を出すための重要な視点です。なぜなら、LPは公開した瞬間がゴールではなく、改善を重ねながら売上や集客を伸ばしていく「成長型の資産」だからです。この章では、LPを投資として考えるべき理由と、費用対効果(ROI)の見方について掘り下げます。
費用対効果(CV・CPA・LTVベースで見る投資回収)
LP制作の効果を正しく判断するには、制作費の“出費”だけを見るのではなく、どれだけ成果(リターン)を生んだかを基準に考えることが欠かせません。
たとえば、LP制作に40万円を投じて、そこから100件の問い合わせが発生したとすれば、1件あたりの獲得コスト(CPA)は4,000円です。もし1件の成約で10万円の売上が生まれるなら、LPが生み出すROIは非常に高いことになります。
LPの投資効果を判断する際に注目すべき指標は、以下の3つです。
- CV(コンバージョン)数:問い合わせ・購入・資料請求などの成果件数
- CPA(Cost per Action):1件あたりの成果獲得コスト
- LTV(Life Time Value):顧客1人あたりの生涯価値
一度作ったLPが継続的に顧客を生み出す仕組みを構築できれば、制作費は早期に回収できます。LPを単なるページ制作ではなく、「売上を生み出す装置」への投資と考えることが、費用対効果を最大化する第一歩です。
A/Bテスト・改善運用が成功を左右する構造
LPは作って終わりではありません。むしろ、公開後の改善サイクルこそが成果を決める重要なプロセスです。
A/Bテストを行い、見出し・ボタン・画像・訴求コピーなどを少しずつ変えながら、コンバージョン率(CVR)を高めていくことが大切です。
この改善運用を支えるのが「データ分析」です。アクセス解析やヒートマップを用いて、どの箇所で離脱が多いか、どの要素が注目されているかを可視化し、仮説と検証を繰り返します。
最初の制作費を安く抑えても、この改善サイクルを回さなければ、LPが本来の力を発揮することはできません。
つまり、LP制作における“真のコスト”は制作費そのものではなく、改善を前提とした運用にかける時間と労力です。短期的な結果だけでなく、半年・1年後にどれだけ成果を上げられるかを見据えて運用体制を設計することが、長期的なROI向上につながります。
長期視点で見た拡張性・改修性・ノウハウ移転
LPを単発の広告ページとして作るか、それとも将来的に自社のマーケティング資産として育てるかによって、投資の価値は大きく変わります。
長期的に効果を発揮するLPを作るには、「拡張性」「改修性」「ノウハウ移転」の3つを意識することが重要です。
拡張性とは、今後サービスや商品ラインナップが増えたときに再利用できる設計であるかどうか。初期段階で柔軟な構成にしておくことで、将来的な修正コストを抑えられます。
改修性とは、公開後に内容を差し替えたり、セクションを入れ替えたりする際のしやすさ。構造が複雑すぎると、更新するたびに費用が発生し、運用効率が悪化します。
ノウハウ移転とは、社内担当者がLP改善の考え方やデータの見方を理解できる状態を指します。制作会社任せにせず、社内で分析・改善を行えるようになることで、LPが持つ「資産価値」は飛躍的に高まります。
LPは“作るもの”ではなく“育てるもの”。
短期の費用に惑わされず、成果が出続けるための構造をつくることこそが、本当の意味での投資回収です。
成果を上げる企業は、常にこの視点を持ってLP制作を進めています。
既存LPの改修・リニューアル費用相場と成功ポイント

新しくLPを制作するだけでなく、既存のランディングページをリニューアルや改修によって改善するケースも増えています。特に広告費が高騰している近年では、「新規制作よりも、既存LPの成果を引き上げるほうがコスト効率が良い」と考える企業が多い傾向にあります。
この章では、リニューアル時の費用相場や、成功に導くための注意点を整理します。
部分改修 vs フルリニューアルの違いと相場目安
LPの改修には大きく分けて「部分改修」と「フルリニューアル」の2種類があります。
部分改修とは、既存の構成やデザインを大きく変えずに、一部の要素だけを修正する方法です。例えば、キャッチコピーの変更、CTAボタンの配置調整、セクションの入れ替えなどが該当します。この場合の費用は5万〜20万円程度が目安で、短期間で改善効果を確認できるのが特徴です。
一方、フルリニューアルは構成やデザイン、コピーまで全面的に見直すケースです。現行ページの課題分析から始まり、訴求軸の再設定やワイヤーフレームの再構築を行うため、30万〜80万円ほどの費用がかかることが一般的です。
ただし、既存LPの素材やデータを再利用できる場合はコストを抑えられるため、制作会社に「どの部分を流用できるか」を確認することが重要です。
リニューアルの目的が“デザインの更新”なのか、“成果改善”なのかによっても、費用配分は大きく変わります。単に見た目を変えるだけではなく、数字に基づく根拠をもとに設計を見直すことが成功への近道です。
改善案設計(分析→課題抽出→テスト設計)
効果的な改修を行うには、まず現状の課題をデータで把握することから始めます。アクセス解析やヒートマップを活用して、「どこで離脱しているのか」「どの要素が注目されていないのか」を明確にしましょう。
次に、課題をもとに仮説を立てます。たとえば「問い合わせボタンが下部にあり、見逃されている」「訴求内容がターゲットとずれている」といった仮説を立て、改善方針を決めます。
この段階では、いきなり全体を作り変えるのではなく、A/Bテストを活用して小さな変更を積み重ねることが有効です。ヘッダーコピーの差し替えやCTAデザインの変更など、1つずつ効果を検証しながら成果を積み上げていくのが理想です。
さらに、改善プロセスを繰り返す中で、データを蓄積し「どんな訴求が反応を得やすいか」という知見を社内に残していくことも大切です。これにより、次回以降の施策に生かせる再現性の高いノウハウが蓄積されます。
改修時に落としがちな注意点(旧構成の引きずり・構造の無理移行など)
リニューアルや改修の際に多い失敗が、「前の構成をそのまま流用してしまう」ケースです。
以前のLPが成果を出していない原因が構成や訴求設計にある場合、そのまま踏襲しても改善にはつながりません。過去のデザインに愛着があっても、一度リセットして構造から見直す姿勢が重要です。
また、旧デザインを無理に新しい構成へ移行すると、レイアウトが崩れたり、表示スピードが低下したりするリスクがあります。コードや画像データをそのまま再利用する場合は、開発面の互換性を確認しておきましょう。
さらに、改修によってURLが変更される場合には、リダイレクト設定やSEO面の引き継ぎにも注意が必要です。せっかくデザインが良くなっても、検索流入を失えば成果は上がりません。
LPのリニューアルで成果を出すためのポイントは、「見た目を整えること」よりも「数字を改善すること」にフォーカスすることです。
そのためには、データをもとに改善方針を立て、仮説検証を繰り返しながら、継続的にチューニングしていく仕組みを整えることが何より重要です。
小さな改修の積み重ねが、長期的な成約率向上につながっていきます。
コストを最適化する工夫と依頼前の準備戦略

LP制作では「いかに費用を抑えるか」よりも、「限られた予算で最大の成果を出すか」が本質的な課題です。
とはいえ、予算が無限にある企業は少なく、多くの発注者が“コストの最適化”に頭を悩ませています。ここでは、品質を落とさず費用を合理的にコントロールするための考え方と、依頼前に準備しておくべきポイントを解説します。
テンプレート/ノーコードLPの活用メリット・落とし穴
テンプレートやノーコードツールを活用すれば、初期費用を大きく削減できます。近年ではデザイン品質の高いテンプレートも多く、初心者でも比較的簡単にLPを作成できます。
特にキャンペーンやイベント用など、短期間だけ使うLPであれば、この方法は非常に有効です。工数を減らせるため、制作費が10万円以下に収まるケースもあります。
しかし、テンプレート活用には明確な限界もあります。レイアウトや構成が固定化されているため、ブランド独自の世界観を表現しづらく、訴求の自由度が低くなることが多いです。また、テンプレートを多用すると「他社と似たデザイン」になり、差別化が難しくなる点も注意が必要です。
ノーコードツールも同様に、修正や拡張がしにくいという課題を抱えています。長期的に運用・改善していくことを考えるなら、最初から柔軟な構造を持つオリジナルLPを制作したほうが、結果的にコスパが良くなることもあります。
社内対応可能な工程を洗い出して外注部分を絞る
費用を抑える最も現実的な方法は、「外注しなくてもできる工程を自社で担う」ことです。
たとえば、テキストライティングや商品説明文、素材写真などを社内で用意すれば、その分の費用を削減できます。
また、ヒアリング用の資料やペルソナ情報、掲載したい実績・口コミなどを事前に整理しておくことで、制作会社の作業時間を減らし、見積もりを下げることも可能です。
ただし、「自社で作れる」と「成果が出る」は別問題。自作の原稿が読みにくくなったり、写真が品質不足だと、かえってコンバージョンを下げる結果になることもあります。
外注と内製の境界線を見極めるには、「専門性」と「手間」のバランスを考えることが大切です。たとえば戦略設計やコピー開発などの専門領域はプロに任せ、素材準備や一次原稿のたたき台作成などは社内で進める、という分担が理想です。
複数社見積もり時に使える比較シート・交渉ポイント
LP制作を依頼する際は、必ず複数社に見積もりを取るようにしましょう。
ただし、単に金額を比べるだけでは意味がありません。比較する際は、「項目別に内容を整理するシート」を作るのがおすすめです。
たとえば次のような項目を軸に比較すると、どの会社が本当にコストパフォーマンスに優れているかが見えやすくなります。
- 提案内容(構成・デザイン・改善支援の範囲)
- 対応スピード・柔軟性
- 修正回数・サポート期間
- 実績・担当者のスキル
- 契約条件・支払いスケジュール
また、見積もり交渉の際には「予算を下げてください」と言うよりも、「この工程を自社で対応するので、その分を調整してほしい」と伝える方が、誠実かつ具体的な交渉になります。
制作会社にとっても、作業内容が明確であればスムーズにコストを見直しやすく、結果的に双方にとって納得感のある見積もりに仕上がります。
改善優先度をつけて段階的に投資する方法
LP制作のすべてを一度に完璧に仕上げる必要はありません。
むしろ、最初に最低限の構成でリリースし、反応を見ながら改善を加えていく“段階的投資”のほうが、リスクを抑えて成果を伸ばしやすい方法です。
たとえば、初期段階では「訴求軸が合っているか」「CTA位置が適切か」など基本的な検証を行い、その結果をもとにコピーやデザインを改修していく流れが理想です。
この手法であれば、初期費用を抑えつつ実データに基づいて改良できるため、“費用のムダ打ち”を防ぐことができます。
また、LP改善は広告運用と連動させることでさらに効果が高まります。広告データからCVRを分析し、どのセクションが成果に貢献しているかを把握することで、次の改修に活かせます。
限られた予算でも成果を出すためには、「安く作る」ではなく「賢く投資する」という発想が欠かせません。
LPは企業の信頼性と売上を左右する重要な資産です。予算の配分を戦略的に設計し、段階的な改善を前提にした制作体制を整えることが、結果的に最もコストパフォーマンスの高い選択となります。
あいみつ相談室がサポートするLP制作・発注支援サービス

LP制作を成功させるためには、「どの制作会社に依頼するか」よりも、自社の目的に合った発注をどう設計するかが何より重要です。
しかし、実際には見積もりの比較や依頼範囲の整理に時間を取られ、どの会社を選べば良いのか分からないまま発注してしまうケースが多く見られます。
そんな悩みを解決するのが、“あいみつ相談室”のLP制作・発注支援サービスです。ここでは、その特徴と強みを詳しく紹介します。
あいみつ相談室とは
あいみつ相談室は、中小企業や個人事業主のための「発注の最適化を支援する相談サービス」です。特定の制作会社に偏らず、ユーザーの課題や目的に合わせて最適な依頼先・依頼方法を提案します。
これまで、Webサイト制作や広告運用、SEO対策など、多様な分野での発注支援を行ってきました。その実績から、「予算を無駄にせず、成果を出すためのLP発注方法が分かる」と多くの相談者から信頼を得ています。
あいみつ相談室が目指すのは、“発注者が後悔しない選択をできる世界”。制作会社と発注者の間に立ち、双方にとって納得できるプロジェクト進行をサポートしています。
対応可能なサービス内容(戦略設計、構成案、制作、実装、改善運用支援 等)
LP制作の支援といっても、単なる「見積もり比較」だけではありません。あいみつ相談室では、依頼前から制作後の改善フェーズまで、LPの全体工程に寄り添うトータルサポートを提供しています。
- 戦略設計・企画支援:目的整理・ターゲット分析・訴求設計をサポート
- 構成案作成・ワイヤーフレーム設計:コンバージョン導線を意識した構成を提案
- 制作・デザイン発注支援:複数社見積もり・依頼書作成・制作会社選定を代行
- コーディング・公開支援:技術要件の整理やCMS対応もサポート
- 改善・運用フェーズ支援:A/Bテスト・効果測定・リニューアル提案まで継続伴走
依頼者が抱えやすい「何をどう頼めば良いか分からない」という不安を解消し、発注プロセス全体を見える化するのが特徴です。
料金プラン・価格目安(相場レンジを踏まえた提示)
あいみつ相談室のサービスは、「相談しやすく、続けやすい価格設定」を大切にしています。初回の相談は無料で、具体的な案件サポートは内容に応じて柔軟に対応しています。
たとえば、
- 見積もり比較・依頼書作成サポート:3〜5万円程度
- 制作会社選定+改善提案プラン:10万円前後
- 制作〜改善フェーズの包括支援:30万円〜
など、相場感を理解した上で、依頼者の予算や目的に合わせた提案を行います。必要以上の費用をかけず、成果に直結するサポートを選べるのが魅力です。
選ばれる理由と差別化ポイント(複数社見積もり支援・ノウハウ提供・成果重視体制など)
あいみつ相談室が他の発注支援サービスと異なるのは、「比較」だけで終わらないことです。見積もりを取りまとめるだけでなく、発注者の立場から“成果につながる判断基準”を共に設計する点に特徴があります。
- 複数社見積もりの最適化サポート
金額だけでなく、構成・サポート・改善体制を比較できるよう整理。納得できる判断を支援します。 - ノウハウ共有と伴走支援
発注後も制作会社とのやり取りや改善施策をサポート。将来的に自社で発注・運用できる力を身につけられます。 - 成果にこだわる支援スタンス
LP制作を「完成させること」ではなく、「成果を出すこと」を目的に、改善と検証を前提にしたアドバイスを行います。
LP制作は、金額やデザインだけでなく、「目的を達成できる仕組みを作るかどうか」が本質です。
あいみつ相談室は、制作会社選びで迷う中小企業・個人事業主の“頼れる伴走者”として、最適なLP発注と成果最大化をサポートしています。
見出しでは語れない“発注前チェックリスト”と判断の軸

LP制作を依頼する前に最も大切なのは、自社の目的と方向性を明確にしておくことです。ここを曖昧にしたまま進めてしまうと、制作会社との認識にズレが生じ、成果につながりにくいページが完成してしまいます。依頼前の準備を整えることで、不要なコストや修正の手間を大幅に減らせます。
目的・KPIの明確化/仮説設計
まずは「何のためにLPを作るのか」を明確にしましょう。商品販売、資料請求、問い合わせ獲得、採用強化など、目的によって最適な構成やトーンは大きく変わります。
KPI(成果指標)も同時に設定しておくことが重要です。たとえば「資料請求50件」「CVR3%」といった数値目標を定めると、制作会社とのゴール共有がしやすくなります。さらに、なぜその数字が妥当かという仮説を立てることで、改善の方向性も明確になります。
競合LPリサーチ・ベンチマーク設定
効果的なLPを作るには、他社の成功事例を研究するのが近道です。競合のLPを複数比較し、デザイン・構成・訴求軸・CTA(ボタン誘導)の違いを分析しましょう。
特に注目すべきは、「上位表示されているLPが何を訴求しているか」「共通している構成要素は何か」という点です。ベンチマークを持つことで、自社が勝負すべき方向が明確になります。
構成・機能要件リスト化・優先順位付け
次に、自社のLPに必要な要素をリストアップします。セクション構成(導入・商品特徴・お客様の声・CTAなど)や、フォーム数・動画有無・SNS連携など、実装したい機能を具体的に書き出しましょう。
ただし、最初からすべてを詰め込みすぎると、ページが冗長になりユーザーが離脱しやすくなります。重要なのは「成果に直結する要素を優先する」こと。目的に合わせて取捨選択し、段階的に拡張していく設計を意識してください。
見積もり比較時の定量/定性評価軸
見積もりを比較する際は、金額の安さだけでなく、“何に価値を感じるか”という軸を持つことが重要です。
定量評価としては「費用」「納期」「修正回数」「サポート範囲」などを、定性評価としては「提案力」「担当者の理解度」「コミュニケーションの質」などを見ます。
この2つの視点をバランス良く判断できれば、金額に惑わされず、結果につながる選択ができるようになります。
契約書・修正回数・権利帰属・保証・保守条件の確認
契約書を交わす際には、細部まで目を通しましょう。特に注意すべきは、以下の5点です。
- 修正回数と対応範囲
- デザインやテキストの著作権・使用権の帰属
- 保守・管理・運用の範囲
- 納品後の保証期間
- 追加修正や更新の費用条件
契約段階であいまいな表現が残っていると、トラブルの原因になります。後で後悔しないためにも、不明点は必ず質問して明確にしておきましょう。
発注前にこれらの準備を整えることで、LP制作は格段にスムーズになります。
要件を明確にしておけば、制作会社の理解も深まり、提案の質が上がります。結果的に「費用対効果の高いLP」を作りやすくなるのです。
あなたのLP投資を後悔しないための選択

LP制作は、単なる「ページを作る作業」ではありません。
それは、企業の未来を左右する“投資判断”です。安さや見た目だけに惑わされず、どのようなLPを作り、どのように育てていくかという「ビジョン」を持つことが、成果を出す企業に共通する姿勢です。ここでは、LP投資を後悔しないための考え方と、行動指針を整理します。
相場を知った上で判断すべき3つのチェックポイント
LP制作を発注する前に、必ず押さえておくべき3つの視点があります。
1つ目は、「目的と成果の整合性」です。
単に“かっこいいデザイン”を目指すのではなく、「このLPで何を達成したいのか」を常に中心に置きましょう。
2つ目は、「投資額に対して得られるリターン」を具体的に想定することです。
制作費が30万円でも100万円でも、そのLPがどれだけの売上やリードを生むのかで費用対効果は変わります。目的が明確なら、相場に惑わされずに“必要な投資”を判断できます。
そして3つ目は、「制作後の改善を前提に考える」こと。
LPは公開して終わりではなく、運用・検証を重ねることで初めて成果が育ちます。改善サイクルを見据えた契約と体制を整えることが、長期的な成功に直結します。
結果を出すLP制作に必要な“5年視点”マインド
LP制作の投資効果を最大化するためには、短期ではなく「5年先を見据えた視点」が必要です。
一時的なキャンペーン用LPであっても、そこで得られたデータやノウハウは次のプロジェクトの財産になります。
制作段階でこの「蓄積の意識」を持つことで、LPは単なる販促物ではなく、企業のマーケティング資産へと成長していきます。
また、制作会社との関係も“一度きりの取引”ではなく、長期的なパートナーシップとして捉えるべきです。改善や再設計を重ねるなかで、制作側が企業の戦略を深く理解し、より成果を出せる関係に進化していきます。
その積み重ねこそが、LPの持つ本当の価値を引き出す鍵になります。
まず動きたい人の最短ロードマップ
「LPを作りたいけど、何から始めればいいか分からない」という方も多いでしょう。
そんなときは、次の3ステップを意識して行動してみてください。
- 現状整理:自社の強み・目的・課題を明確化する
- 比較・相談:複数の制作会社から見積もりを取り、内容と費用のバランスを確認する
- 伴走支援を受ける:発注に不安がある場合は、あいみつ相談室のような中立的サポートを活用する
この3ステップを踏めば、闇雲に探すよりも早く、自社に合った制作パートナーと出会うことができます。特に初めてLPを発注する場合、プロの視点を一度挟むことで、予算の無駄や方向性のブレを防げます。
LP制作は「安く済ませるか」ではなく、「どれだけ成果に結びつけられるか」で判断するものです。
そのためには、目先の費用にとらわれず、自社の成長戦略に沿った“長期投資”として捉える姿勢が欠かせません。
最初の一歩を踏み出す勇気と、正しい判断軸を持つことで、LP制作は確実に事業の未来を変える力になります。
今こそ、自社にとって最も価値あるLP投資を選び取るタイミングです。